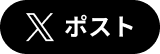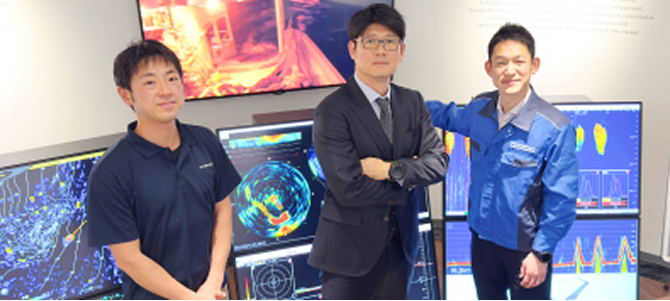未来を想像し、新しい技術の可能性を切り拓く——そんな挑戦が、古野電気の「未来の技術デザイン委員会」では日々行われています。今回は、その活動の中心を担った金丸さんと長岡さんにお話を伺い、未来の技術デザイン委員会が思い描く未来をどうビジュアル化したのか語っていただきました。
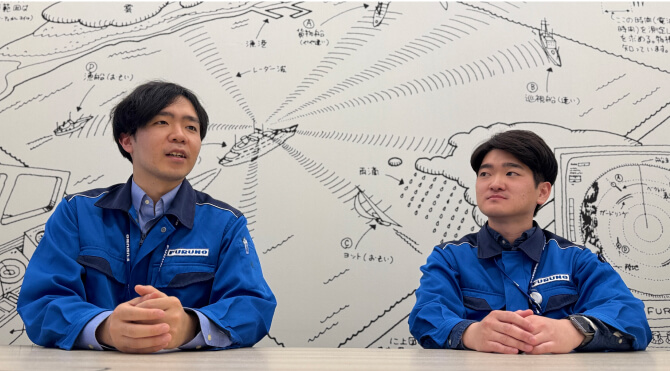
(左)金丸 直弘さん
2020年入社。自律航行システム開発部。VRナビゲーションシステムの開発を担当。
(右)長岡 瞭太さん
2020年入社。航空・防衛事業部 開発部 水中音響機器を担当。
「2050年の船のブリッジを考えて」そんな一言からはじまった
──未来の技術デザイン委員会はどのように始まったのでしょうか?
金丸さん:事業部長からの「2050年の船のブリッジを考えてほしい。」そんな一言から始まりでした。ただ、単なるブリッジの設計ではなく、「そもそも2050年の社会ってどうなってるんだろう?」という根本的な問いに発展していきました。
未来の技術デザイン委員会の第1回が開催されたのは2022年。研究部、舶用機器事業部、システム機器事業部などの部署から、若手の技術者が10名集まりました。そのときは、とにかくスケールの大きな未来を描こうということで、「海の上で生活する未来」や「持続可能な海洋都市」といったコンセプトが生まれました。技術者だけでなく、デザイナーと協力しながら未来のビジョンをビジュアル化しました。
──なぜ未来の技術デザイン委員会を設立する必要があったのでしょうか?
金丸さん:技術者として未来を描くとき、専門的な視点に偏りがちなので、他の部署とイメージを共有しやすい形にする必要があると感じました。
また、「2050年の会社がこうなってたら面白いよね!」という未来をみんなで考えられる場にしたかった。こういう活動を次世代のリーダーたちが受け継いでいけば、技術開発や営業など、みんなが同じ方向を向いて進めるんじゃないかなと思っています。

──第2回目の未来の技術デザイン委員会ではどんなことを考えましたか?
長岡さん:私は第2回からの参加でしたが、第2回ではより具体的な「2035年の世界」に焦点を当て、2050年の未来を実現するために必要な技術を整理しました。
たとえば、「2050年に完全な自動運航船が当たり前になるなら、2035年の時点ではどのレベルまで進んでいるべきか?」とか、「海洋都市のエネルギー供給はどうなっているのか?」といったテーマについて議論しました。そうすると、「再生可能エネルギーの活用が重要だよね」とか、「AIやセンサー技術の進化がカギを握るよね」という話に自然とつながっていきました。
──第1回と第2回の違いは?
金丸さん:第1回はとにかく「ワクワクする未来を自由に考える場」でした。第2回は「その未来に向けて、今から何をすべきか?」という実践的な視点が強くなったと思います。
長岡さん:そうですね。2050年の理想像を描いたうえで、「じゃあ2035年にはどこまで到達しているべき?」と逆算して考えました。より近い未来を描くことで、実際の技術ロードマップにもつなげやすくなりました。
加えて、2050年に求められる社会の価値観やライフスタイルの変化も議論しました。気候変動への対応として再生可能エネルギーの活用、AIによる船舶の自動運航システムの導入など、技術だけじゃなく社会全体の変化を見据えた議論ができたのがよかったですね。
ぶっ飛んだアイデアを生み出せ!未来を描く挑戦
──アイデア出しの過程で苦労された点はありますか?
長岡さん:技術者って、どうしても現実的な視点になりがちなんですよね。でも、未来を描くには、それじゃダメだと思って、あえて「ぶっ飛んだ発想」を意識しました。たとえば、魚が嫌がる音波を出して網の代わりにする養殖のアイデアとか、水中ドローンを使って魚を誘導する技術とか、普通に考えたら突飛すぎる話です。でも、そういう発想から新しい技術の種が生まれるんですよね。
また、未来の海上都市では、常に波の影響を受けるので、どうやって揺れを抑えるかっていう課題が出てきます。それに対して「耳の中に石を入れて三半規管の影響を調整する」なんてアイデアが出てきたこともありました。こうやって、技術とアイデアを掛け合わせることで、どんどん新しい未来像が広がっていくのが面白かったですね。

アイデアを現実に!未来デザインの影響と実現可能性
──生まれたアイデアはどのように活用されていますか?
金丸さん:実は、未来の技術デザイン委員会で生まれたアイデアのいくつかは、すでに社外パートナーとの協業につながっています。たとえば、ブルーカーボン(海洋環境の再生)に関する研究が進んでいて、港のヘドロ化問題を解決するための協力依頼が来ているんです。
さらに、技術ロードマップにも影響を与えていて、新しい技術開発の方向性がどんどん明確になっています。未来の技術デザイン委員会で生まれた発想が、企業全体の共通言語になり、次のプロジェクトにつながるケースも増えていますね。
長岡さん:単なる研究開発じゃなくて、会社全体の方向性を示す役割も果たしていると思います。実際、委員会で検討されたアイデアのいくつかは、プロジェクトの立ち上げの参考にもなっています。
特に、海上都市の構想や水中ドローンを活用した養殖システムなんかは、現実の技術開発と結びつきやすく、実際に実用化の可能性を探る動きも出てきています。
──技術者の視点から見て、この活動の意義はどこにありますか?
金丸さん:未来を考えるって、技術の方向性を明確にするだけじゃなくて、社内のモチベーションにもつながるんですよ。「自分たちの技術が未来を変えるかもしれない」って思えると、日々の業務の取り組み方も変わってきます。
長岡さん:そうですね。それに、今までの技術開発では出てこなかったような発想が生まれるのも大きなメリットです。未来の技術デザイン委員会を通じて、技術者が自由にアイデアを出し合うことで、新しい可能性がどんどん広がるのを実感しています。
2050年の未来を描く——変わり続ける当たり前を作る
──お二人が思い描く2050年の未来と、今後の活動について教えてください。
金丸さん:僕が目指しているのは、「未来の新しい当たり前を創ること」です。2050年には、フルノが生み出した技術が当たり前のように使われている世界になっていたらいいなと思っています。未来を考える活動は、答えが決まっているわけじゃなくて、常に変化し続けるものだからこそ、続ける意味があるんですよね。
こういう活動ができるのは、今までの人たちがしっかり地盤を固めてくれたからです。無駄をなくして利益を出してくれたからこそ、未来を考える余裕がある。その利益をもとに、僕らが新しい未来を作っていくチャンスをもらえているので、しっかり頑張りたいですね。
長岡さん:2050年には、無人機が陸・海・空すべてで活躍し、センサー技術がそれを支える世界になっていると思います。でも、それを実現するには、技術だけでなく、未来を考えられる人がもっと増えていくことが大事なんじゃないかと感じています。
技術開発は、一本の道を進むんじゃなくて、幹からいろんな芽が生まれるものです。開発者はその「幹」をしっかり持ちつつ、新しい技術を生み出していく。そのバランスを大事にしながら、ワクワクする未来を考え続けたいですね。
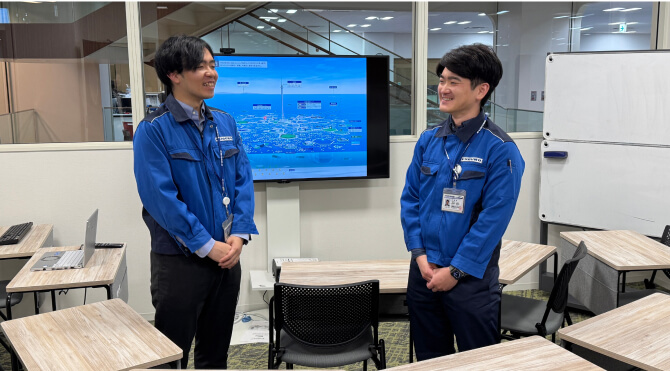
未来は、描いた瞬間から変わり続けるものだからこそ、考え続けることに意味がある——そうお二人の言葉から強く感じました。